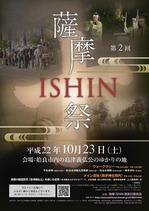スポンサーサイト
上記の広告は90日以上記事の更新がないブログに表示されます。新しい記事を書くことで、こちらの広告が消せます。
2010年09月30日
会場イベントについて
精矛神社境内のメイン会場では、島津義弘公ゆかりのイベントを開催いたします。
午後3時~午後6時
1.島津義弘公が分かるブース(パネル、動画など展示)
2.太鼓演奏(吹上青松太鼓)
3.薩摩琵琶弾奏 他
午後3時~午後6時
1.島津義弘公が分かるブース(パネル、動画など展示)
2.太鼓演奏(吹上青松太鼓)
3.薩摩琵琶弾奏 他
2010年09月30日
お帰りの際の公共交通機関
精矛神社会場でのイベント終了予定時刻は18時となっております。
お帰りの際には、参道を直進し踏み切りをわたってすぐの橋を右折し、そのまま直進すれば加治木駅となります。
→地図で確認
【乗換え案内】10月23日(土)
加治木駅 →鹿児島駅→鹿児島中央駅 360円
18:08出発 18:41着(詳細 goo路線)
18:47出発 19:21到着(詳細 goo路線)
加治木駅 → 国分駅 220円
18:08出発 18:19到着(詳細 goo路線)
18:47出発 18:57到着(詳細 goo路線)
お帰りの際には、参道を直進し踏み切りをわたってすぐの橋を右折し、そのまま直進すれば加治木駅となります。
→地図で確認
【乗換え案内】10月23日(土)
加治木駅 →鹿児島駅→鹿児島中央駅 360円
18:08出発 18:41着(詳細 goo路線)
18:47出発 19:21到着(詳細 goo路線)
加治木駅 → 国分駅 220円
18:08出発 18:19到着(詳細 goo路線)
18:47出発 18:57到着(詳細 goo路線)
2010年09月30日
駐車場について
2010年09月30日
精矛神社会場へお越しの皆様
精矛神社へのアクセスは、加治木駅が最寄り駅となっております。
駐車場はございませんので、JRにてお越しください。
【乗換え案内】10月23日(土)
鹿児島中央駅→鹿児島駅→加治木駅 450円 (詳細 goo路線)
13:56出発 14:26到着
国分駅 → 加治木駅 220円(詳細 goo路線)
14:37出発 14:49到着
精矛神社へのアクセスへ
駐車場はございませんので、JRにてお越しください。
【乗換え案内】10月23日(土)
鹿児島中央駅→鹿児島駅→加治木駅 450円 (詳細 goo路線)
13:56出発 14:26到着
国分駅 → 加治木駅 220円(詳細 goo路線)
14:37出発 14:49到着
精矛神社へのアクセスへ
2010年09月30日
中止の場合
2010年09月30日
薩摩ISHIN祭ウォークラリー集合場所
集合場所(地図): 重富小学校(島津義弘公居館、平松城跡)
日時: 平成22年10月23日(土)8時30分受付開始
9時出陣式、9時30分出発
※雨天の場合には中止致します。
【乗換え案内】10月23日(土)
鹿児島中央駅→鹿児島駅→重富駅 360円 (詳細 goo路線)
8:08出発 8:28到着
国分駅 → 重富駅 360円(詳細 goo路線)
9:21出発 9:42到着
※重富駅より南国バスが出ております。帖佐駅行き[姶良小循環]
重富駅前8:51→重富麓8:55 バス停より徒歩5分
*重富麓バス停の場所はコチラでご確認ください。
※重富駅より徒歩20分
※集合場所を含め、駐車場はございませんので、公共交通機関等をご利用になり
お越し下さい。
google ストリートビューで下見に行く
日時: 平成22年10月23日(土)8時30分受付開始
9時出陣式、9時30分出発
※雨天の場合には中止致します。
【乗換え案内】10月23日(土)
鹿児島中央駅→鹿児島駅→重富駅 360円 (詳細 goo路線)
8:08出発 8:28到着
国分駅 → 重富駅 360円(詳細 goo路線)
9:21出発 9:42到着
※重富駅より南国バスが出ております。帖佐駅行き[姶良小循環]
重富駅前8:51→重富麓8:55 バス停より徒歩5分
*重富麓バス停の場所はコチラでご確認ください。
※重富駅より徒歩20分
※集合場所を含め、駐車場はございませんので、公共交通機関等をご利用になり
お越し下さい。
google ストリートビューで下見に行く
2010年09月30日
幟の意味

なぜISHIN祭の幟が黒に白抜きの十文字なのか?というご質問をよくいただきます。
尚古集成館には義弘所用軍旗と呼ばれる、黒地に丸十の軍旗が残されています。また、津軽家本の関ヶ原合戦屏風では、黒地に筆文字の十の絵が残されているため、こちらを採用しました。
一般的に知られているのは、写真左奥の白地に丸十ですが、息子の家久のものとも言われているそうです。
参考:歴史群像シリーズ特別編集 【決定版】図説・戦国武将118
2010年09月26日
薩摩ISHIN祭とは
「薩摩ISHIN祭」は、戦国武将 島津義弘公を顕彰し、その生き様から現代を生きるヒントを学ぼうということで鹿児島と東京の若手で協力して2009年からスタートしたお祭りです。
内容は、姶良市内にある島津義弘公の所縁の地を巡るウォークラリーと、ウォークラリーのゴールでもある島津義弘公を祀る精矛神社(くわしほこじんじゃ)境内における様々な企画となっています。
薩摩ISHIN祭という名前の由来は、島津義弘公の号の「惟新(いしん)」と、暗いニュースが多い現代社会に薩摩から風を起こし(「一新」)し、平成の世に「維新(いしん)」を起こしていくという3つの意味を込めています。
内容は、姶良市内にある島津義弘公の所縁の地を巡るウォークラリーと、ウォークラリーのゴールでもある島津義弘公を祀る精矛神社(くわしほこじんじゃ)境内における様々な企画となっています。
薩摩ISHIN祭という名前の由来は、島津義弘公の号の「惟新(いしん)」と、暗いニュースが多い現代社会に薩摩から風を起こし(「一新」)し、平成の世に「維新(いしん)」を起こしていくという3つの意味を込めています。
2010年09月24日
薩摩ISHIN祭オリジナル ストラップ

「敵中突破Tシャツ」のロゴをあしらった、カワイイ オリジナルストラップができました! 薩摩ISHIN祭の精矛神社で販売予定です! 「カワイイ♩」と評判は上々です!
2010年09月23日
西郷どんの遠行に参加しました

今年は映画「半次郎」で盛り上がる中、毎年の恒例行事、「西郷どんの遠行(せごどんのえんこ)」が行われました。
今年は薩摩ISHIN祭でもだいぶお世話になっている方のお手伝いとして、薩摩ISHIN祭スタッフが応援に行きました。
朝から天候が崩れていたので開催が心配されましたが、無事に終えたとの報告がありました。
薩摩ISHIN祭の幟も殿軍ではためいていたことでしょう。
2010年09月23日
会場内ブース説明
精矛神社会場のブースは、以下のとおりです。
●義弘公ブース
●FC KAGOSHIMA:店舗でTシャツやタオル販売
●ふるまい鍋:錦江鍋を限定100食
●お茶:お茶、お菓子の提供だけでなくお菓子をのせる皿が龍門司焼(ISHIN祭特製)販売
●本部:龍門司焼き、帖佐人形、かじきまんじゅうと薩摩ISHIN祭グッズ販売
●焼酎:焼酎の試飲と限定焼酎「精矛」販売
●キャンピングカーブース:駐車場で展開
●薩摩剣士隼人:PR活動
●義弘公ブース
●FC KAGOSHIMA:店舗でTシャツやタオル販売
●ふるまい鍋:錦江鍋を限定100食
●お茶:お茶、お菓子の提供だけでなくお菓子をのせる皿が龍門司焼(ISHIN祭特製)販売
●本部:龍門司焼き、帖佐人形、かじきまんじゅうと薩摩ISHIN祭グッズ販売
●焼酎:焼酎の試飲と限定焼酎「精矛」販売
●キャンピングカーブース:駐車場で展開
●薩摩剣士隼人:PR活動
2010年09月22日
第2回 薩摩ISHIN祭ポスター

第2回薩摩ISHIN祭のポスターが完成しました。
各地でお見かけすることがあるかと思います。
QRコードを使って、こちらの公式ブログへアクセスすることも可能になりました。
まだブログ内の整理が十分でないので、ご不自由かけますが、近日使いやすくまとめる予定です。
2010年09月19日
【限定焼酎】御神酒「精矛」
10月23日に開催される薩摩ISHIN祭の公式グッズの一つになります。
島津義弘公を祀る神社、精矛(くわしほこ)神社の御神酒として作られました。
限定生産1500本ですが、これは関ヶ原合戦(1600年)のときの島津軍の軍勢1500名に由来しているのだそうです。焼酎の色が淡い青色の透き通った色となっているそうで、神秘的です。
義弘公の勇猛果敢な敵中突破にあやかって、合格祈願やお祝い事などの贈答品にいかがでしょうか。


【お問い合わせ】
株式会社鹿児島蔵や
電話 099-814-3105
メールでのお申し込みはコチラ
島津義弘公を祀る神社、精矛(くわしほこ)神社の御神酒として作られました。
限定生産1500本ですが、これは関ヶ原合戦(1600年)のときの島津軍の軍勢1500名に由来しているのだそうです。焼酎の色が淡い青色の透き通った色となっているそうで、神秘的です。
義弘公の勇猛果敢な敵中突破にあやかって、合格祈願やお祝い事などの贈答品にいかがでしょうか。


【お問い合わせ】
株式会社鹿児島蔵や
電話 099-814-3105
メールでのお申し込みはコチラ
2010年09月19日
薩摩剣士 隼人、お披露目会




先日の薩摩ISHIN祭プレイベントでご協力いただいた、新ローカルヒーロー「薩摩剣士 隼人」のプレスリリースの様子です。
テレビ放送の予定もあるとのことです。
薩摩ISHIN祭当日も会場にやってきます♪お楽しみに。
2010年09月12日
薩摩ISHIN祭プレイベント・レビュー
本日開催された、薩摩ISHIN祭プレイベントは約150名の方々が暑い中、足をお運びいただきました。この場をお借りして御礼申し上げます。
私が会場に到着したのは16時すぎていました。
おしゃれな一室が会場で、入ってすぐに薩摩ISHIN祭のイメージビデオと、島津義弘公物語を再生してました。すぐ後ろにはパネルが並び、右側には幟とグッズ販売コーナー。




薩摩琵琶弾奏と天吹吹奏や甲冑の講義があり、希望者の方には試着をさせてもらうコーナーもありました。
ちょうど空いているときでしたので、親子で甲冑姿になり、記念撮影。
すると、新ローカルヒーロー、薩摩剣士 隼人が甲冑武者とともに帰ってきました♪

どうやらこの薩摩剣士 隼人は本日コスチュームができたばかりとかで、記念すべき日がこのイベントだったということでした。娘はおじけることなく、真ん中に立って記念撮影に応じていました♪
パネルと動画を担当して、出来上がりが気になっていましたが、ディスプレイもすばらしく、ちゃんとした展示会になっていたことがうれしかったです。スタッフの皆様、お疲れ様でした。ありがとうございました。ぜひ本祭もこの調子でがんばりましょう!
私が会場に到着したのは16時すぎていました。
おしゃれな一室が会場で、入ってすぐに薩摩ISHIN祭のイメージビデオと、島津義弘公物語を再生してました。すぐ後ろにはパネルが並び、右側には幟とグッズ販売コーナー。




薩摩琵琶弾奏と天吹吹奏や甲冑の講義があり、希望者の方には試着をさせてもらうコーナーもありました。
ちょうど空いているときでしたので、親子で甲冑姿になり、記念撮影。
すると、新ローカルヒーロー、薩摩剣士 隼人が甲冑武者とともに帰ってきました♪

どうやらこの薩摩剣士 隼人は本日コスチュームができたばかりとかで、記念すべき日がこのイベントだったということでした。娘はおじけることなく、真ん中に立って記念撮影に応じていました♪
パネルと動画を担当して、出来上がりが気になっていましたが、ディスプレイもすばらしく、ちゃんとした展示会になっていたことがうれしかったです。スタッフの皆様、お疲れ様でした。ありがとうございました。ぜひ本祭もこの調子でがんばりましょう!
2010年09月10日
薩摩ISHIN祭プレイベント
マルヤガーデンズ「ガーデンイベント 薩摩ISHIN祭プレイベント」HP
●開催時間
2010年9月12日(日)11:00〜18:30
●開催場所
地階7階 マルヤガーデンズ(旧 三越)garden7
大きな地図で見る
●イベントタイトル
薩摩ISHIN祭プレイベント
●イベントサブタイトル
薩摩の戦国武将「島津義弘公」を知ろう!
●主催団体名 正式名称
薩摩ISHIN祭実行委員会
●イベント内容
昨年から姶良市で開催している薩摩ISHIN祭の本祭開催の前に、島津義弘公という武将やお祭りの内容を少しでも知って頂こうと考えています。特に、戦国時代を少しでも体験頂けるように、子ども鎧の体験コーナーや甲冑武者との記念撮影などのコーナーもあり、大人から子どもまで楽しめるような企画があります。
●定員
特になし。但し、甲冑体験企画やビデオ講演の際には入場を制限させて頂く場合もございます。
●申込み方法・申込み先
予約不要 当日先着順
●参加費 ・入場料
無料
●お問合わせ先
薩摩ISHIN祭実行委員会 吉留大輔 090-4983-6365
●開催時間
2010年9月12日(日)11:00〜18:30
●開催場所
地階7階 マルヤガーデンズ(旧 三越)garden7
大きな地図で見る
●イベントタイトル
薩摩ISHIN祭プレイベント
●イベントサブタイトル
薩摩の戦国武将「島津義弘公」を知ろう!
●主催団体名 正式名称
薩摩ISHIN祭実行委員会
●イベント内容
昨年から姶良市で開催している薩摩ISHIN祭の本祭開催の前に、島津義弘公という武将やお祭りの内容を少しでも知って頂こうと考えています。特に、戦国時代を少しでも体験頂けるように、子ども鎧の体験コーナーや甲冑武者との記念撮影などのコーナーもあり、大人から子どもまで楽しめるような企画があります。
●定員
特になし。但し、甲冑体験企画やビデオ講演の際には入場を制限させて頂く場合もございます。
●申込み方法・申込み先
予約不要 当日先着順
●参加費 ・入場料
無料
●お問合わせ先
薩摩ISHIN祭実行委員会 吉留大輔 090-4983-6365
2010年09月07日
鹿児島若モンの集い@銀座
薩摩ISHIN祭実行委員で企画した銀座飲み会を辛島美登里さんのブログに取り上げて頂きました。
http://ameblo.jp/karashimamidori/entry-10641735773.html
本日9/7の記事です。
http://ameblo.jp/karashimamidori/entry-10641735773.html
本日9/7の記事です。
2010年09月03日
【薩摩ISHIN祭PR隊】ラジオ出演決定
マルヤガーデンズのイベントがあと2週間に迫る中、FM出演が決まりました。
フレンズFM フレンズマンション201号室 Mr.BPと福元さん
http://fm201.jp/
という番組です。
7日(火)の16:00〜16:48の番組です。
聞ける方は、ぜひチューナーを合わせてお待ちください!周波数は76.2です。
フレンズFM762
http://www.friendsfm.co.jp/
フレンズFM フレンズマンション201号室 Mr.BPと福元さん
http://fm201.jp/
という番組です。
7日(火)の16:00〜16:48の番組です。
聞ける方は、ぜひチューナーを合わせてお待ちください!周波数は76.2です。
フレンズFM762
http://www.friendsfm.co.jp/
2010年09月02日
【イベント】薩摩ISHIN祭プレイベント
本日開催された、薩摩ISHIN祭プレイベントは約150名の方々が暑い中、足をお運びいただきました。この場をお借りして御礼申し上げます。
 おしゃれな一室が会場で、入ってすぐに薩摩ISHIN祭のイメージビデオと、島津義弘公物語を再生してました。薩摩琵琶の弾奏やちょうど15時ごろより甲冑の講義があり、希望者の方には試着をさせてもらうコーナーもありました。
おしゃれな一室が会場で、入ってすぐに薩摩ISHIN祭のイメージビデオと、島津義弘公物語を再生してました。薩摩琵琶の弾奏やちょうど15時ごろより甲冑の講義があり、希望者の方には試着をさせてもらうコーナーもありました。



ちょうど空いているときでしたので、親子で甲冑姿になり、記念撮影。
すると、新ローカルヒーロー、薩摩剣士 隼人が甲冑武者とともに帰ってきました♪
どうやらこの薩摩剣士 隼人は本日コスチュームができたばかりとかで、記念すべき日がこのイベントだったということでした。娘はおじけることなく、真ん中に立って記念撮影に応じていました♪
パネルと動画を担当して、出来上がりが気になっていましたが、ディスプレイもすばらしく、ちゃんとした展示会になっていたことがうれしかったです。スタッフの皆様、お疲れ様でした。ありがとうございました。ぜひ本祭もこの調子でがんばりましょう!

 おしゃれな一室が会場で、入ってすぐに薩摩ISHIN祭のイメージビデオと、島津義弘公物語を再生してました。薩摩琵琶の弾奏やちょうど15時ごろより甲冑の講義があり、希望者の方には試着をさせてもらうコーナーもありました。
おしゃれな一室が会場で、入ってすぐに薩摩ISHIN祭のイメージビデオと、島津義弘公物語を再生してました。薩摩琵琶の弾奏やちょうど15時ごろより甲冑の講義があり、希望者の方には試着をさせてもらうコーナーもありました。


ちょうど空いているときでしたので、親子で甲冑姿になり、記念撮影。
すると、新ローカルヒーロー、薩摩剣士 隼人が甲冑武者とともに帰ってきました♪
どうやらこの薩摩剣士 隼人は本日コスチュームができたばかりとかで、記念すべき日がこのイベントだったということでした。娘はおじけることなく、真ん中に立って記念撮影に応じていました♪
パネルと動画を担当して、出来上がりが気になっていましたが、ディスプレイもすばらしく、ちゃんとした展示会になっていたことがうれしかったです。スタッフの皆様、お疲れ様でした。ありがとうございました。ぜひ本祭もこの調子でがんばりましょう!

2010年09月01日
薩摩ISHIN祭への誘い
昨年第1回目を開催した薩摩ISHIN祭は、今年は10月23日(土)に実施すべく準備を進めている。薩摩ISHIN祭、はじめて耳にしたという方も多いと思うが、島津義弘公を顕彰することで、その生き様から現代を生きるヒントを学ぼうということでスタートした鹿児島と東京の若手で協力して立ち上げたお祭りである。内容は、姶良市内にある島津義弘公の所縁の地を巡るウォークラリーと、ウォークラリーのゴールでもある島津義弘公を祀る精矛神社(くわしほこじんじゃ)境内における様々な企画となっている。薩摩ISHIN祭という名前の由来は、島津義弘公の号の「惟新(いしん)」、明治「維新(いしん)」の2つ言葉にある。お祭りの概略説明はここまでにして、当日、是非足を運んで頂くためにも、今日は姶良市内にある島津義弘公の所縁の地について簡単にご紹介して行きたいと思う。
まずは島津義弘公の説明から…
島津義弘公は島津氏15代島津貴久公の次男として亀丸城(日置市)に生まれた。初陣は天文23年(1554年)岩剣城の攻防戦である。その後、九州の桶狭間の戦いと言われる木崎原の戦い、豊後の大友氏を破った耳川合戦、明の軍勢から鬼島津と恐れられた朝鮮出兵、そして「島津の退き口」で有名な関ヶ原の戦いなど、50回以上も出陣を重ねた。その武功が有名な武将であるが、お茶への造形も深く、千利休に師事したり、朝鮮から連れ帰った陶工に好みの茶碗を焼かせたり、自ら茶道具を作成したりという面もある。
初陣の地「岩剣城跡」(麓には平松城跡):ウォークラリー出発予定地点
天文23年(1554年)、蒲生勢との戦いの中で、島津義弘公が初陣を飾った城である。その際には伝来したばかりの鉄砲が使用されたことでも有名。麓にある平松城跡は、慶長年間に島津義弘公が居館とした場所で石垣などが残っている。
関ヶ原の戦い前後に住んでいた場所「帖佐御屋地跡(ちょうさおやじあと)」:ウォークラリー休憩予定地点
栗野から居所を移した場所で10年近く住んでいた場所。近くには朝鮮陶工「金海」によって築かれた宇都窯跡や愛馬である膝つき栗毛の墓などもある。
晩年を過ごした地「加治木館跡」:ウォークラリー通過地点
慶長12年(1607年)から元和5年(1619年)に85才で亡くなるまで住んだ館である。御里窯跡(おさとかまあと)、龍門司焼古窯といった焼き物に関する史跡、義弘公が亡くなった時に殉死した家臣に関する史跡である実窓寺磧、後藤塚や庄内の乱の伊集院忠真(いじゅういん ただざね)の墓や加治木、鹿児島の区割りなどに助言をした江夏友賢(こうか ゆうけん)の墓など、関係する方のお墓や史跡も近郊に多く存在する場所である。
島津義弘公を祀る神社「精矛神社」;ウォークラリーゴール地点
義弘公の神号である精矛厳健雄命(くわしほこいつたけおのみこと)から名付けられている神社である。明治2年に加治木館内に作られた神社が大正7年
の没後300年の際に現在の地に移る。現在の場所は、元々島津義弘公が兄である島津義久公の為に用意した土地であったところを加治木島津家が所有しており、その地を提供した。境内には、文禄の役の際に朝鮮から持ち帰ったといわれる手洗鉢と石臼がある。現在の宮司は加治木島津家当主 島津義秀氏。
以上。(参考は姶良・伊佐地域広域観光マップ「戦国武将島津義弘を訪ねる」、並びに第1回薩摩ISHIN祭配布資料 等)
このように姶良市内の史跡は、ひとつひとつ調べると島津義弘公の人柄を感じるような史跡も多い。薩摩ISHIN祭では地元姶良市の観光ガイドの皆様による説明なども実施(昨年度実績)しており、より学べる環境を作っている。
最後に、何故、今、島津義弘公なのかということを書いて終わりにしたい。島津義弘公は、ご存知の通り、戦国時代の武将である。彼の生き様を追体験して心身を鍛えたのが「妙円寺詣り」などの鹿児島の伝統的なお祭りである。今年のNHK大河ドラマが「龍馬伝」ということもあり、幕末に目がいきがちではあるが、あの時代の教科書であったのはまさに島津義弘公、その人であった。幕末の志士達が学んだ島津義弘公を、我々も学ぶことで、少しでも私たちも同じ目線を持てるようになりたい。その想いである。
薩摩ISHIN祭実行委員会代表
吉留大輔
まずは島津義弘公の説明から…
島津義弘公は島津氏15代島津貴久公の次男として亀丸城(日置市)に生まれた。初陣は天文23年(1554年)岩剣城の攻防戦である。その後、九州の桶狭間の戦いと言われる木崎原の戦い、豊後の大友氏を破った耳川合戦、明の軍勢から鬼島津と恐れられた朝鮮出兵、そして「島津の退き口」で有名な関ヶ原の戦いなど、50回以上も出陣を重ねた。その武功が有名な武将であるが、お茶への造形も深く、千利休に師事したり、朝鮮から連れ帰った陶工に好みの茶碗を焼かせたり、自ら茶道具を作成したりという面もある。
初陣の地「岩剣城跡」(麓には平松城跡):ウォークラリー出発予定地点
天文23年(1554年)、蒲生勢との戦いの中で、島津義弘公が初陣を飾った城である。その際には伝来したばかりの鉄砲が使用されたことでも有名。麓にある平松城跡は、慶長年間に島津義弘公が居館とした場所で石垣などが残っている。
関ヶ原の戦い前後に住んでいた場所「帖佐御屋地跡(ちょうさおやじあと)」:ウォークラリー休憩予定地点
栗野から居所を移した場所で10年近く住んでいた場所。近くには朝鮮陶工「金海」によって築かれた宇都窯跡や愛馬である膝つき栗毛の墓などもある。
晩年を過ごした地「加治木館跡」:ウォークラリー通過地点
慶長12年(1607年)から元和5年(1619年)に85才で亡くなるまで住んだ館である。御里窯跡(おさとかまあと)、龍門司焼古窯といった焼き物に関する史跡、義弘公が亡くなった時に殉死した家臣に関する史跡である実窓寺磧、後藤塚や庄内の乱の伊集院忠真(いじゅういん ただざね)の墓や加治木、鹿児島の区割りなどに助言をした江夏友賢(こうか ゆうけん)の墓など、関係する方のお墓や史跡も近郊に多く存在する場所である。
島津義弘公を祀る神社「精矛神社」;ウォークラリーゴール地点
義弘公の神号である精矛厳健雄命(くわしほこいつたけおのみこと)から名付けられている神社である。明治2年に加治木館内に作られた神社が大正7年
の没後300年の際に現在の地に移る。現在の場所は、元々島津義弘公が兄である島津義久公の為に用意した土地であったところを加治木島津家が所有しており、その地を提供した。境内には、文禄の役の際に朝鮮から持ち帰ったといわれる手洗鉢と石臼がある。現在の宮司は加治木島津家当主 島津義秀氏。
以上。(参考は姶良・伊佐地域広域観光マップ「戦国武将島津義弘を訪ねる」、並びに第1回薩摩ISHIN祭配布資料 等)
このように姶良市内の史跡は、ひとつひとつ調べると島津義弘公の人柄を感じるような史跡も多い。薩摩ISHIN祭では地元姶良市の観光ガイドの皆様による説明なども実施(昨年度実績)しており、より学べる環境を作っている。
最後に、何故、今、島津義弘公なのかということを書いて終わりにしたい。島津義弘公は、ご存知の通り、戦国時代の武将である。彼の生き様を追体験して心身を鍛えたのが「妙円寺詣り」などの鹿児島の伝統的なお祭りである。今年のNHK大河ドラマが「龍馬伝」ということもあり、幕末に目がいきがちではあるが、あの時代の教科書であったのはまさに島津義弘公、その人であった。幕末の志士達が学んだ島津義弘公を、我々も学ぶことで、少しでも私たちも同じ目線を持てるようになりたい。その想いである。
薩摩ISHIN祭実行委員会代表
吉留大輔